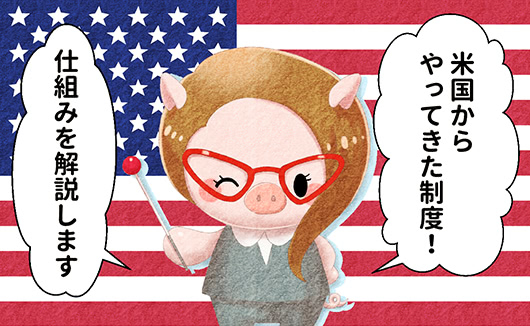
企業型確定拠出年金とは?掛金を決める前に知りたい仕組みと制度
日本の代表的な企業年金には、確定給付企業年金と企業型確定拠出年金があります。あなたの会社の企業年金はどの制度を採用しているかご存知でしょうか?
もし企業型確定拠出年金であったとしてもどのような制度なのか完璧に理解できている人は少ないでしょう。
しかし実は老後資金となる退職金を増やすも減らすも、企業型確定拠出年金の加入者であるあなた次第なんです。
ここでは企業型確定拠出年金にスポットをあてて、基本的な仕組みをはじめ、税制優遇や、運用方法、口座管理などにかかる手数料、受け取り方などをメリットとデメリットを交えてご紹介します。
企業型確定拠出年金は社員自らが運用する制度
企業型確定拠出年金(企業型DC)とは、企業が掛金を毎月積み立てて、社員が自分で年金資産の運用を行う制度です。
社員は自分で金融商品を選んで年金資産の運用を行うため、運用成績によって将来の退職金が変動することになります。
この制度を利用できるのは厚生労働大臣から企業型年金規約の承認を受けた企業のみ。さっそく企業型確定拠出年金の概要について解説していきましょう。
確定拠出年金はアメリカからやってきた制度
確定拠出年金は、2001年に創設された年金制度で、主に次の4つの特徴があげられます。
- 企業の他、個人や社員が掛金を積み立てる制度があること
- 掛金を掛け過ぎないために掛金額の上限が設定されていること
- 中途退職時の給付がないこと
- 個人の自己責任で給付額が決まること
なお、確定拠出年金は「401K」と呼ばれることが多いですが、アメリカの内国歳入法第401条K項では税制優遇が定められており、日本はアメリカのこの規定を見本として制定したことが理由とされています。
また確定拠出年金は「DC」とも呼ばれます。それは「Defined Contribution Plan(確定拠出年金)」の略称から来ているからなんですね。
企業型確定拠出年金の加入者は約680万人
企業型確定拠出年金の加入資格は会社によって異なる
企業型確定拠出年金に加入できる人は、厚生労働大臣より企業型年金規約の承認を受けた企業の厚生年金の被保険者であることが必要です。
ただし、企業型年金規約に次の4つの要件に基づいて加入資格を定めることができます。自分の会社の加入資格を確認しておきましょう。
- 一定の職種(営業職や事務職など)に属する社員のみを対象
- 一定の勤続年数(3年や5年など)の社員のみを対象
- 一定の年齢(50歳以上)の社員は加入対象外
- 希望する社員が加入対象
1.一定の職種(営業職や事務職など)に属する社員のみを加入対象とする
もし非正社員(アルバイト・パート等)で対象外とされた人は、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することが可能です。
2.一定の勤続年数(3年や5年など)の社員のみを加入対象とする
この場合、入社時より一定の勤続年数までの期間については確定拠出年金と同等額の給付(前払い退職金制度など)を行うことが義務付けられています。
3.一定の年齢(50歳以上)の社員を加入対象外とする
一定年齢以上の社員は、資産運用の期間が短くなるため、万一、短期的な市場の下落があった場合、目減りしたまま退職を迎えるリスクがあるためです。
4.希望する社員を加入対象とする
確定拠出年金は、原則として中途退職者は一時期を受け取ることができないため、加入自体を任意で選択することが認められています。
ただし加入を希望しない方に対しては加入者と同等額の給付(前払い退職金制度など)を行うことが義務付けられています。
企業型確定拠出年金の資産は転職すると転職先に持っていける
転職先に「企業型確定拠出年金」があれば転職先で移換することができますが、なければ「個人型確定拠出年金」へ移換することになります。
もし転職先に「確定給付型企業年金」があった場合、その会社が「企業型確定拠出年金」の資産を受け入れるルールがあるのであれば、移換することが可能です。
つまり転職の際、企業型確定拠出年金がどうなるかは転職先の企業年金制度に応じるということです。
ちなみに自営業者や公務員となった場合は、個人型の確定拠出年金に移換することができます。
企業型確定拠出年金は3つの税制上の優遇を受けることができる
企業型確定拠出年金には拠出時、運用時、受給時それぞれに税制上の優遇措置が設けられています。
- 拠出時の掛金が非課税
- 運用時の運用益が非課税
- 受給時の給付金が各種控除の対象
それでは具体的にどのような税制の優遇を受けることができるのか見ていきましょう。
会社負担の掛金・社員負担の掛金は全額非課税
企業型確定拠出年金における会社が負担する掛金は給与扱いとはならないため、全額非課税となります。一方、掛金と同じ金額を給与で受け取った場合は、給与所得として税金(所得税・住民税)がかかることになります。
さらに企業型確定拠出年金は、会社の掛金に上乗せして、社員本人も掛金を積み立てることができます。この場合、社員の掛金については全額が所得控除の対象となるため、所得税および住民税の課税がありません。
企業型確定拠出年金の掛金は社会保険料の対象外
確定拠出年金における会社が負担する掛金は社会保険料の対象にもなりません。
例えば確定拠出年金の掛金月2万円(年間24万円)の代わりに、毎月の給与に上乗せして受け取った場合、社会保険料はどうなるでしょうか?
そもそも社会保険料は、標準報酬月額表によって標準報酬月額が決められています。この標準報酬月額は老齢厚生年金額や病気になった時などの補償の基準になっているんですね。
そのためもし積み立て分を給与から差し引くことになると、標準報酬月額も減少し結果的に厚生年金も減少する可能性があるのです。
企業型確定拠出年金の運用益は全額非課税
一般的な金融商品で資産運用を行うと、利益に対して20.315%の税金がかかりますが、確定拠出年金の運用で得た利益に対しては全額非課税となります。
受け取るときには所得控除が受けられる
確定拠出年金に積み立ててきた資産は60歳以降に一時金または年金で受け取ることになりますが、いずれの場合でも次の税制優遇を受けることができます。
(1)一時金の場合は退職所得として退職所得控除を受けられる
退職所得控除の計算方法は次のとおりです。
原則、確定拠出年金(一時金)と他の退職所得を合計して退職所得控除額を計算します。
(2)年金の場合は雑所得として公的年金等控除が受けられる
公的年金等控除の計算方法は次のとおりです。
公的年金等には公的年金や確定給付企業年金に加えて、確定拠出年金の老齢給付金(年金)などが含まれます。
企業型確定拠出年金の掛金には限度額がある
次に企業型確定拠出年金の掛金について理解しましょう。
確定拠出年金の掛金には限度額が決められている
確定拠出年金は税制の優遇を受けることができるため、掛金を多くしたいと思われる方も少なくないかもしれません。しかしながら、法律によって拠出限度額が決められており、限度額を超える掛金は認められていません。
拠出限度額(月額)は次のとおりです。
| 掛け金の限度額 | |
|---|---|
| 企業型確定拠出年金のみの場合 | 55,000円(※1) |
| 確定給付型の年金と併用している場合 | 27,500円(※2) |
※2:個人型年金への加入を認める場合は15,500円
選択型確定拠出年金とマッチング拠出の違いとは?
企業型確定拠出年金の掛金は、原則として毎月、拠出限度額の範囲で企業が掛金の全額を拠出することになります。
しかしながら企業型確定拠出年金の中には次のような制度もあります。会社にこのような制度が適用されているか確認しておきましょう。
1. 選択型確定拠出年金
社員が給料の一部を拠出限度額の範囲内で自ら決めた金額を拠出することができる制度です。
拠出額は3,000円以上1,000円単位で拠出することができ、ライフスタイルに合わせて拠出額を変更することができます。老後資金の自助努力を支援する制度といえます。
2. マッチング拠出
企業が拠出する掛金に上乗せして社員自らが拠出することができる制度です。拠出額は企業の拠出額を上限に個人で拠出することができます。
ただし法定の拠出上限額を超えることはできません。また、マッチング拠出制度は任意加入です。
| 選択制確定拠出年金 | マッチング拠出 | |
|---|---|---|
| 社員の拠出上限額 | 55,000円 | 27,500円 |
| 所得税・住民税 | 課税対象外 | 課税対象外 |
| 社会保険料など | 課税対象外 | 課税対象 |
確定拠出年金にかかる手数料は5種類ある
- 加入時・移換時手数料
- 口座管理手数料
- 給付事務手数料
- 還付事務手数料
- 信託報酬
毎月かかる料金は僅かですが、長期間にわたると何万円も変わってくることも珍しくありません。どのような手数料がいくら位かかるのかを理解しておくことが大切です。
それぞれの手数料を詳しく見ていきましょう。
(1)加入時・移換時手数料
個人型確定拠出年金に加入したり、企業型確定拠出年金に加入していた社員が退職して転職先の確定拠出年金(企業型・個人型)に移換する場合には、国民年金基金連合会に対して一律2572円(税別)の手数料(一時金)がかかります。
なお運営管理機関によっても加入時・移換時の手数料がかかる場合があります。
(2)口座管理手数料
口座管理手数料は、掛金の徴収や資産管理、運用指図の取りまとめ、加入者へのサポート費用などで専用口座の維持に必要な手数料です。
| 種類 | 支払先 | 年間金額(税込) |
|---|---|---|
| 事務手数料 | 国民年金基金連合会 | 1,236円 |
| 資産管理手数料 | 信託銀行 | 768円 |
| 運営管理手数料 | 運営管理機関 | 金融機関によって変わる |
個人型確定拠出年金加入者の場合は、口座管理手数料を自分で支払う必要がありますが、企業型の場合は会社が負担することになります。
企業型の場合は、金融機関を選択することはできませんが、個人型の場合は、運営管理手数料の安い金融機関を選ぶことも大切といえます。
3.給付事務手数料
給付事務手数料は、給付金を受け取る時にかかる手数料です。給付一回につき432円かかりますので、年金での受け取りを希望される場合は、給付事務手数料も考慮して受け取り回数を決めましょう。
4.還付事務手数料
還付事務手数料は、法令限度額を超えて拠出された時など還付が生じた場合にかかる手数料です。国民年金基金連合会の還付事務手数料は1,029円、事務委託先金融機関の場合は432円です。
5.信託報酬
信託報酬は、金融商品選びの際に投資信託を組み合わせた場合にかかる運用会社などの資産運用における手数料です。
信託報酬は運用商品ごとに料率が異なり、資産残高が多くなればなるほど高くなります。
そのため、長期間の運用の際には留意しておきたい手数料の一つといえます。
企業型確定拠出年金の資産運用の考え方
確定拠出年金は、加入者自らが、適切な金融商品を選択して適切な運用を行うことが必要です。
企業型確定拠出年金の場合は、規約ごとに運用商品が一般的に20本程度決められており、その中から社員は組み合わせて選択することになります。
また企業は社員に対する継続的な投資教育が義務付けられているため、運用スキルを身に付けながら定期的に運用商品の見直しをはかることができます。
運用商品には「元本確保型商品」と「元本変動型商品」がある
企業型確定拠出年金の場合、規約ごとに運用商品が決められていますが、運用商品は3本以上かつ、1本以上は元本確保型商品を用意しておくというルールが定められています。
元本確保型商品は積み立てた元本が確保されるもので、具体的には「定期預金」と「保険」があります。
一方で元本変動型商品は元本が運用によって変動するもので、「投資信託」があります。運用成績によって資産を増やすことができる反面、元本割れのリスクがあります。
元本割れが心配で「元本確保型商品」だけを選ぶ人も多いでしょう。どの商品をどのような組み合わせで選ぶのが正解というものはありませんので、自由に選ぶことができるのも確定拠出年金の魅力の一つといえます。
しかし元本確保型の場合、満期期間によって金利が異なるので、満期の異なる商品を選んだ方が良いですし、金融機関の破綻のリスクを考えると2社以上の商品を選んでおく方がおすすめです。
加えて低金利状態が続けば、老後資金を増やすことは難しいことも考えておきましょう。
元本割れのリスクは分散投資で回避!
投資信託の投資先は、国内・外国株式や国内・外国債券、不動産など様々あって、それぞれリスクとリターンが異なります。つまり、分散して投資を行えばリスクも分散されるということです。
ですが企業型確定拠出年金の場合は、企業でも定期的な投資教育があると思いますので少しずつ勉強していくことも必要だと思いますよ。
確定拠出年金の受け取り方法は4種類
確定拠出年金は、老後資金の準備を目的としているため、老齢給付金は原則60歳以降でなければ引き出すことはできません。
ここでは、確定拠出年金の受け取り方について理解しましょう。
- 老齢給付金
- 障害給付金
- 死亡一時金
- 脱退一時金
それぞれの受け取り方について詳しく解説していきます。
(1)老齢給付金
原則として60歳以降に給付請求を行い、年金資金を受け取ることができる給付金です。受取方法は、年金(5年以上20年以下)、一時金、年金と一時金の併用のいずれかとなります。
ただし、満60歳時点で通算加入者等期間が10年ない場合は、最大65歳まで受取開始年齢が繰り下がります。
(2)障害給付金
障害基礎年金を受給できる程度の障害がある場合は、60歳前でも年金資金を受け取ることができる給付金です。受取方法は、年金または一時金のいずれかとなります。
(3)死亡一時金
確定拠出年金に年金資産がある状態で加入者が亡くなった場合、親族などの遺族が受け取ることができる一時金です。特に指定がない場合は、受取順位は配偶者・子・父母・孫・祖父母または兄弟姉妹となります。
(4)脱退一時金
確定拠出年金は、原則として60歳まで途中の引き出しや脱退はできません。ただし、次の脱退要件をすべて満たす場合に限って、脱退をして一時金を受け取ることができます。
- 企業型・個人型確定拠出年金の加入者または運用指図者でないこと
- 個人別管理資産額が15,000円以下であること
- 加入者の資格喪失日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと
上記の要件を満たさなかった場合でも、個人型確定拠出年金の脱退要件を満たすことができれば脱退することができます。
企業型確定拠出年金の脱退は難しい
もし脱退したとしても60歳までは運用するということを考え、口座管理手数料などのランニングコストを用意しておきましょう。
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違い
確定拠出年金には企業型と個人型があります。ここでは両者を比べてみましょう。
企業型確定拠出年金/iDeCo(個人型確定拠出年金)比較表
企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金を簡単に比較すると次の表のとおりです。
| 企業型確定拠出年金 | 個人型確定拠出年金 | |
|---|---|---|
| 加入 | 企業の退職金制度 | 自分の意思 |
| 掛金の拠出 | 原則、会社負担 | 原則、自己負担 |
| 拠出限度額(月額) | ・企業年金なし:55,000円 ・企業年金あり:27,500円 |
・企業年金なし:23,000円 ・企業年金あり: ・確定給付型年金:12,000円 ・企業型年金:20,000円 |
| 金融機関の選択 | 会社が選択 | 自分が選択 |
| 運用商品 | 会社が準備した商品より選択 | 自分が契約した金融機関が準備した商品より選択 |
| 口座管理料 | 原則、会社負担 | 自己負担 |
企業型確定拠出年金とiDeCoは併用できる!
2017年1月に制度が改正されて併用できるようになったばかりのため、規約変更を行っている企業は多くはないと思いますが、まずは規約を確認しておくことが必要です。
ただし、マッチング拠出をしている場合はiDeCoと併用することはできません。
iDeCoについては次の記事でも詳しく解説しています。
企業型確定拠出年金と確定給付企業年金の違い
企業型確定拠出年金と同じ企業年金の制度として確定給付企業年金があります。いずれも同じような制度ですので、簡単に違いを説明しておきましょう。
企業型確定拠出年金と確定給付企業年金との大きな特徴の違いは、企業型確定拠出年金は「拠出額」を先に決定するのに対して、確定給付企業年金は「給付額」を先に決定する点です。
ここではそれぞれのメリットとデメリットに分けて確認していきます。
企業型確定拠出年
- 個人別の年金口座があるため、年金資産の残高を把握することができる
- 万一、会社の業績が悪化したり、倒産しても自分の年金資産は確保される
- 離職や転職時に年金資産を持ち運ぶことができる
- 運用実績が良ければ将来の給付額を増やすことができる
- 年金資産の運用は社員自身が行う必要がある
- 運用に失敗した場合は社員自身に責任があるため企業は保障してくれない
- 運用実績が悪ければ元本割れの可能性がある
- 将来の給付額が運用実績によって変動するため、受取見込み額が確定できない
- 原則、60歳まで受け取ることができない
確定給付企業年金
- 年金資産の運用は会社が行うため、運用を気に掛ける必要がない
- 運用が失敗した場合、企業が保障してくれる
- 将来の給付額が確定しているため、安定した老後資金を得ることができる
- 個人別の年金資産の残高を把握することができない
- 万一、会社の業績が悪化した場合などは、給付額が減額される可能性がある
企業型確定拠出年金は加入者である社員自体が資金を運用するもの。一方で確定給付企業年金の場合、資金は個人で運用することはできません。
確定給付企業年金をもっと知りたい人は次の記事をチェックしてみてくださいね。
老後資金を増やすのも減らすのもあなた次第!
確定給付企業年金と異なり、将来もらえる金額が決まっているわけではないため、どうしても元本割れのリスクを考えてしまいますが、拠出時・運用時・受取時のそれぞれに税制面で非課税というメリットがありますし、確かな知識をもって、運用を行えば着実に老後資金を増やすことができます。
確定拠出年金制度自体、20年に満たない制度ではありますが、法改正を繰り返して拠出限度額の引き上げや、利便性の向上などが行われた結果、企業数、加入者数ともに上昇傾向にあり、今後の企業年金の主流といえます。
老後資金を手堅く増やすのも、多少のリスクをとるのも、あなた次第です。
だからこそ、自ら情報収集を行った上で確定拠出年金制度を上手に活用することがとても大切だといえます。




