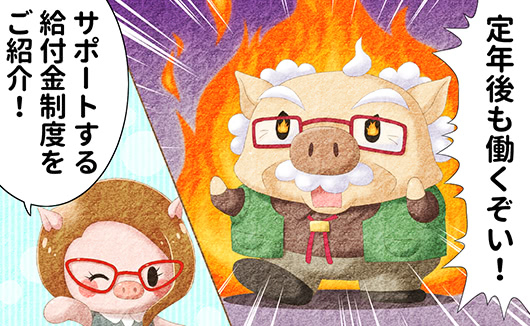
高年齢雇用継続給付とは?定年後も働き続けるなら知るべきお金の制度
老後資金の一つとして多くの方が頼りにしている老齢年金ですが、老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴って、会社は60歳定年以降も継続して65歳までは雇用することを義務付けられるようになりました。
しかしながら、定年後も今までと同じ給料で働ける場合は多くありません。
そこで定年後に下がった給料の一部を補うことができる「高年齢雇用継続給付」という制度が設けられました。
この記事では、60歳の定年後も働き続ける方に向けて「高年齢雇用継続給付制度」をわかりやすく解説します。定年退職後も安心して働き続けることができるよう、受け取れる条件や金額・期間、年金との支給調整をしっかり把握しておきましょう。
2種類ある高年齢雇用継続給付
「高年齢雇用継続給付」には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
高年齢雇用継続基本給付金とは
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の従業員が、60歳以降も基本手当(失業保険)などを受け取らないで、原則として60歳以降の給料が60歳時点の賃金と比べて75%未満に減少した状態で働き続ける場合に受け取ることができる給付金です。
高年齢再就職給付金とは
60歳以降会社を退職後、基本手当を受け取って再就職した際の賃金が、基本手当の基準となった日額の30倍と比べて75%未満に減少した状態で働き続ける場合に受け取ることができる給付金です。この場合、失業保険の支給残日数が100日以上あることが必要となります。
それぞれの給付金は記事の後半でさらに詳しく解説します。
高年齢雇用継続基本給付金のしくみ
それでは高年齢雇用継続給付のうち、まずは「高年齢雇用継続基本給付金」の仕組みについて説明していきましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の受給要件
高年齢雇用継続基本給付金は、基本手当(再就職手当などを含む。)を受け取っていない従業員を対象として、原則として60歳時点の賃金と比べて、60歳以後の賃金が75%未満となっており、次の2つの要件を満たせば給付金を受け取ることができます。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
- 5年以上の雇用保険の被保険者であった期間があること
高年齢雇用継続基本給付金の給付額を計算しよう
低下率=(支給対象月に受け取った賃金月額)÷(60歳到達時の賃金月額)×100
60歳到達時の賃金月額が、次の上限額472,200円以上となる場合や下限額74,400円未満となる場合はこの上限額または下限額を使用して計算します。なお、この上下限金額は平成30年8月1日以後の金額であり、毎年改定されます。
みなし賃金とは?支給対象月に減額された賃金も含まれる
支給対象月に受け取った賃金にはみなし賃金を含みます。みなし賃金とは次のような理由により欠勤や遅刻・早退をして賃金の減額があった場合であっても、減額された額が支払われたものとする賃金をいいます。
- 本人の都合(冠婚葬祭など)
- 病気やケガ
- 会社都合の休業
- 妊娠、出産、育児
- 介護
- 低下率が61%以下の場合の支給率=15%
- 低下率が62%以上75%未満の場合の支給率=(-183÷280×支給対象月に受け取った賃金額)+(137.25÷280×賃金月額)
- 低下率が75%以上の場合の支給率=0%
賃金月額と支給率・低下率がわかれば、高年齢雇用継続基本給付金の金額が導き出されます。
ちなみに支給金額には限度額があり、最低限度額は1,984円、最大限度額は359,899円となっています。(平成30年8月1日以降)
高年齢雇用継続基本給付金の手続きの流れ
高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには次の流れで申請手続きを行うことが必要です。
- 従業員が会社に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出
- 会社が「受給資格確認票・(初回)支給申請書」をハローワークに提出
- ハローワークが会社に「受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書」「支給申請書(2回目分)」を交付
- 会社が従業員に「受給資格確認通知書・支給(不支給)決定通知書」「支給申請書(2回目分)」を交付
- 支給が決定されたら、ハローワークから従業員の口座に給付金が振り込まれる
2回目以降の支給申請には受給資格確認手続きは不要です。
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、原則として2ヶ月ごとにハローワークから指定された月に支給申請書を提出することが必要となります。なお、初回の支給申請については最初に支給を受ける支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に行うことも可能です。
支給申請書の提出は初回を除いて指定された支給申請月中に行う必要がありますので注意が必要です。
高年齢再就職給付金のしくみ
次に高年齢雇用継続給付のうち、「高年齢再就職給付金」の仕組みを解説していきましょう。
高年齢再就職給付金の受給要件
高年齢再就職給付金とは基本手当を受給し再就職した従業員を対象としています。基本手当を受給した後、60歳以後に再就職をし、再就職後の各月に支払われる賃金が「基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった場合」、次の5つの要件を満たせば給付金を受け取ることができるのです。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者である
- 基本手当についての算定基礎期間が5年以上ある
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
- 1年を超えて引き続き雇用されることが確実な職業に就いた
- 同一の就職について、再就職手当の支給を受けていない
高年齢再就職給付金の給付額と受給期間
実際に計算式を見ていきましょう。
低下率=再就職後の賃金÷前職の賃金月額×100
前職の賃金月額が、上限額472,200円以上となる場合や下限額74,400円未満となる場合はこの上限額または下限額を使用して計算します。なお、この上下限金額は平成30年8月1日以後の金額であり、毎年改定されます。
- 低下率が61%以下の場合の支給率=15%
- 低下率が62%以上75%未満の場合の支給率=(-183÷280×再就職後の賃金)+(137.25÷280×前職の賃金月額)
- 低下率が75%以上の場合の支給率=0%
高年齢再就職給付金額は賃金月額と支給率で割り出すことができます。
支給限度額は最低1,984円、最高359,899円です。(平成30年8月1日以降)
ただし、高年齢再就職給付金は基本手当の残日数が再就職日の前日から200日以上の場合は、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、残日数が100日以上200日未満の場合は、再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで受け取ることができます。
なお受給期間中に65歳となった場合は、仮に受給期間が残っていても65歳に到達した月までしか受け取ることはできません。
高年齢再就職給付金の手続きの流れ
次の流れで申請手続きを行いましょう。
- 従業員が会社に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出
- 会社が「受給資格確認票・(初回)支給申請書」をハローワークに提出
- ハローワークが会社に「受給資格確認通知書」「支給申請書」を交付
- 会社が従業員に「受給資格確認通知書」「支給申請書」を交付
- 従業員が会社に「支給申請書」を提出
- 会社がハローワークに「支給申請書」を提出
- ハローワークが会社に「支給(不支給)決定通知書・支給申請書(次回分)」を交付
- 会社が従業員に「支給(不支給)決定通知書・支給申請書(次回分)」を交付
- 支給が決定された場合、ハローワークから従業員の口座に振り込まれる
一連の申請手続きは、原則として会社経由で行う必要がありますが、従業員本人が希望する場合は、自ら申請手続きを行うことができます。
高年齢再就職給付金の支給を受けるには、原則として2ヶ月ごとにハローワークから指定された月に支給申請書を提出することが必要となります。なお、初回の支給申請については最初に支給を受ける支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内に行うことも可能です。
支給申請書の提出は初回を除いて指定された支給申請月中に行う必要がありますので注意しましょう。
高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できない
同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件を満たした場合でも併給することはできず、どちらか一方を選択することが必要となります。
高年齢再就職給付金と再就職手当の主な違いは次のとおりです。
| 高年齢再就職給付金 | 再就職手当 | |
|---|---|---|
| 支給額 | 再就職後の賃金月額×最大15% | 支給残日数×基本手当日額×60%または70% |
| 支給方法 | 原則2ヶ月毎(最大2年間) | 一括支給 |
| 老齢厚生年金の支給停止 | あり | なし |
高年齢雇用継続給付を受け取ると老齢厚生年金の一部が停止される
高年齢雇用継続給付を受ける60歳以上65歳未満の従業員で特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)をもらっている方は、
在職による年金の支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付の給付額に応じて、年金の一部が支給停止される場合があります。
具体的な支給停止額は次の計算式で計算できます。
低下率=60歳以降の賃金(標準報酬月額)÷60歳到達時の賃金月額×100
1.賃金の低下率が75%以上の場合または、標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合
高年齢雇用継続給付が支給されないため、支給停止額はありません。
2.賃金の低下率が61%超え75%未満の場合
逓減率=(-183×低下率+13,725)÷280×100÷低下率×6÷15
計算が面倒な場合は「60歳到達時の賃金月額」に対する「標準報酬月額」の割合に応じた年金の支給停止率早見表を確認することもできます。
3.賃金の低下率が61%以下の場合
高年齢雇用継続給付の支給率が15%であっても、在職老齢年金の停止率が6%なので、実質的には9%の給付率となります。
なお、老齢基礎年金については本来65歳からの支給となりますが、仮に繰り上げて65歳よりも前からもらっていたとしても停止されることはありません。
60歳以降の働き方を考えておくことが必要!
60歳の定年以降も今までと同じように働いて同程度の給料をもらえる方については、高年齢雇用継続給付を考える必要はありません。
しかしながら、定年後は働き方を変えたい、または会社のルール上、労働条件が変わるというような方については、あなた自身の60歳以降の働き方(社会保険の加入を継続した働き方なのか就労日数や就労時間数を少なくした働き方なのか)や給料、年金額などを総合的に考えることが必要となります。
最近では、70歳までの雇用義務化にむけて検討されている状況ですので、今後の動きにも注意をしておくとよいでしょう。


