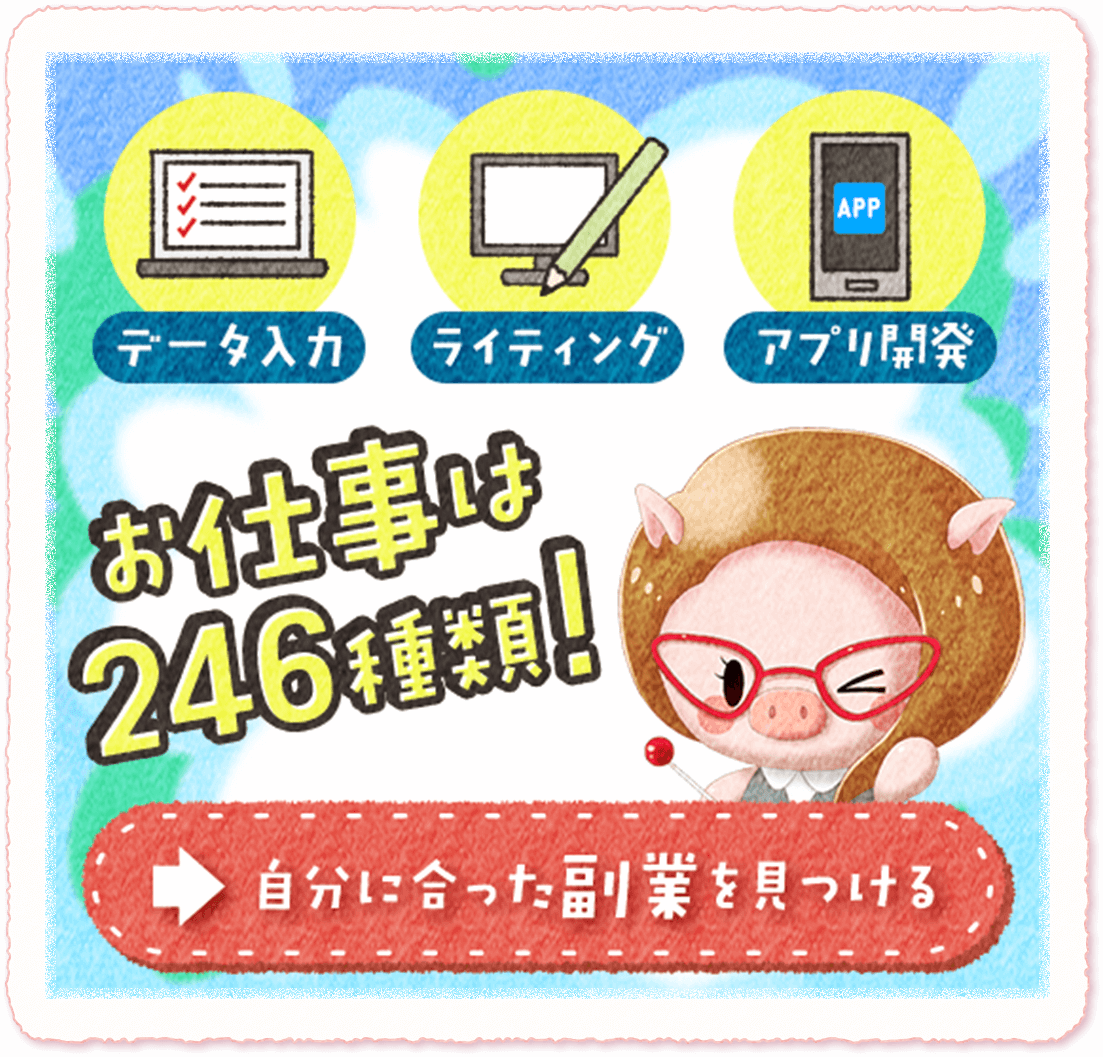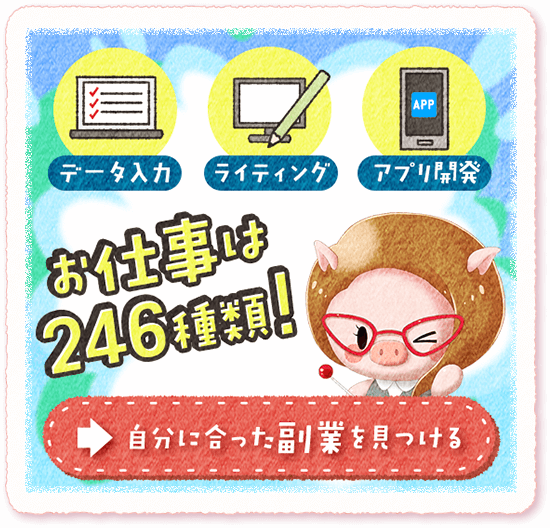副業で税金はいくらかかる?知っておくべき所得税と住民税の考え方
本業で働きつつ、副業で稼いでいるという方。収入が増えたのはいいけれど、気になるのは税金のことではないでしょうか。
副業をすることで発生する税金は、住民税と所得税の2つ。
住民税は副業での所得が少しでも発生すると、市区町村に申告し住民税の額を確定してもらう必要があります。
所得税の場合は副業の種類にもよるものの、副業での所得金額が20万円以下の場合は申告する必要がなく税金がかからないことが多いです。しかし副業による所得が20万円を超える場合には、税務署に申告し所得税を支払わなければなりません。
実は副業によって税金の計算方法は異なるもの。確定申告など支払い方法も含め、副業と税金の関係について一緒に学んでいきましょう。
副業で納める税金は所得税と住民税の2つ
副業をすることで支払う義務が発生する税金は、所得税と住民税の2つ。
所得税は、所得がある人ならば誰もが支払う必要がある、所得にかかる税金のこと。ただし、この場合の所得とは収入のことではありません。
所得とは、収入から必要な経費を差し引いた金額のこと。収入がいくらあっても控除や経費が多くあり控除後の所得が少なくなれば、所得税の額は低くなります。
住民税も所得にかかる税金です。ただし、所得税と違う点は前年度の所得に対して税金を支払わなければならないこと。そのため、今年度いくら所得が少なくても前年度の所得が多額だった場合には、高い住民税を支払う必要があります。
副業している方必見!自分の副業の所得税について知っておこう
副業している人が気になるのは、税金を支払う必要があるのかないのか、税金がいくらなのかということですよね。では、副業について所得税がかかるのかかからないのか、税金がいくらになるのか、計算方法などをシミュレーションしてみましょう。
副業の種類によって所得の計算方法は異なる!
所得税を支払う必要があるのかないのか、金額はいくらなのかを知るにはまず、自分の副業がどのような所得にあたるのか知っておく必要があります。
というのも、所得の種類によって、収入の金額から所得の金額を算出する計算方法が異なるもの。
おもな所得の種類を紹介しましょう。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
自分の副業がこの10種類の所得のうち、どの所得にあてはまるのかを知っておく必要があります。
副業の種類とあてはまる所得、いくらから確定申告をして税金を支払う必要があるのかといったことや所得の計算方法などは、以下のとおり。
| 副業の種類 | 所得の種類 | 確定申告が必要なケース | 所得金額の計算方法 |
|---|---|---|---|
| アルバイト・ パート |
給与所得 | 収入の金額に関わらず確定申告が必要 | 給与合計金額-給与所得控除額 |
| 株式を売却して利益を得た | 譲渡所得 | 源泉徴収口座以外で株式を売却して利益を得た場合など | 譲渡価額-必要経費(取得費+手数料)-特別控除額(50万円) |
| 株の配当金の場合 | 配当所得 | 会社員は原則確定申告の必要なし | 収入金額-元本を取得する際に負債があった場合の利子 |
| 家賃収入・駐車場経営 | 不動産所得 | 所得金額が20万円を超える場合 | 収入金額-必要経費 |
| フリマアプリ(※) | 生活用動産の譲渡による所得 | なし | なし |
| ブログ・アフィリエイト・ 原稿料・仮想通貨・FXなど |
雑所得または事業所得 | 所得が20万円を超える場合 | 収入金額-必要経費(-青色申告特別控除) |
課税対象の所得金額に税率を掛けて所得税の金額を出そう!
分離課税となる所得は、山林所得と土地や建物、株の譲渡所得、利子所得。これらの所得については、それぞれの所得金額に対し税額を算出しなければなりません。
総合課税の場合は、「所得の合計金額」-「所得控除の金額」=「課税対象の所得金額」という計算をすることで所得金額を出すことができます。
所得控除とは、生命保険料控除や医療費控除など、それぞれの人が生活していくために必要な費用を所得から差し引くこと。所得の合計金額から所得控除の金額を引くことで、所得税の課税対象となる所得金額が決まります。
課税対象の所得金額がわかれば、所得対象金額に所得税の税率を掛けることで所得税を算出できます。
日本は累進課税制度という所得が高くなればなるほど税率が高くなる制度を取り入れているんです。所得による税率は以下のとおり。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
この表にある税率を所得にかけることで、所得税の金額を算出することができます。
所得税の申告は確定申告で行おう!
副業の所得税は、確定申告をすることで申告することができます。
確定申告とは、1月~12月までの収入などを計算し所得税の金額を確定させる手続きのこと。
確定申告書を決められた期間内に税務署に提出することで手続きをすることができます。e-Taxという方法を使えば、ネットで申告を行うことも可能です。
確定申告をするには、まず確定申告書という書類を作成しなければなりません。国税庁の確定申告書作成コーナーにアクセスすると、簡単に作成することができます。
確定申告書の作成が完了すれば、決められた期間内に税務署に提出しましょう。2019年の場合、確定申告を行うことができる時期は2月18日(月)~3月15日(金)まで。毎年2月中旬から3月の中旬までの間が確定申告を行うことができる時期です。
見落としがちな副業にかかる住民税について詳しく知ろう!
20万円を超えなければ確定申告が不要であるうえ所得税を支払う必要がないことも多い副業での収入。ですが、それはあくまでも所得税の場合。
住民税の場合、副業で少しでも収入があれば、住民税を支払う必要があります。
住民税を算出する計算式は以下のとおり。
住民税を支払う必要がある人ならば誰もが同じ金額を支払う必要がある住民税のこと。地方自治体によって異なり、4,000円~5,000円程度であることが多いようです。
住民税は確定申告をすると税務署から自動的に各自治体に通知されます。ただし、副業による所得が20万円を下回り、確定申告をする必要がなかった場合には、市区町村役場で直接所得申告をしなければなりません。
サラリーマンで本業として勤務している会社において住民税を天引きされている場合(特別徴収の場合)は、5月頃に本業の会社に対して、住民税の額の通知がきます。そして、通常副業の分も合わせた住民税が、6月~翌年の5月まで毎月、本業の給料から天引きされます。
少額でもバレる可能性大!副業の未申告・脱税は危険
「副業での稼ぎは少額だし、バレることはないだろう」と考えてしまう人もいるかもしれません。
本来ならば確定申告をし、所得税や住民税の申告をしなければならない立場であるのにしなかった場合、副業していたことがバレると所得税や住民税に加え、延滞税も支払わなければなりません。
また、所得を隠していたとみなされると、重加算税という税金も支払う必要があります。
事実を隠していたために与えられるペナルティのような税金のこと。追加本税の35~40%も支払う必要がある負担の大きな税金です。
副業の申告をしなかった場合、これらの税金を支払わなければならない可能性もあります。副業の税金がいくらだったのかなどと税金を節約することなど考えず、副業の所得が20万円以上あった場合は、必ず申告するようにしましょう。
副業をするならば税金について詳しく知っておこう!
副業による所得があり税金を支払う必要があるにも関わらず申告をせず税金を支払わなかった場合、脱税がバレると延滞税などの税金を支払う必要が出てきます。また、所得隠しを疑われた場合には、重量課税という重い税金を支払わなければならない可能性も。
副業による所得はバレないから大丈夫などと軽く思わず、税金は支払わなければならないものと考え、きちんと申告をして税金を支払いましょう。