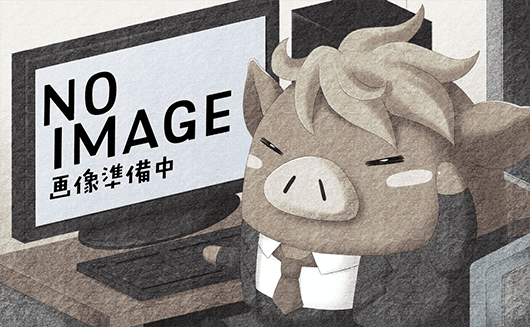
死亡届とは?届け人になれる人の条件と提出時に必要な手続き
ご家族が亡くなった場合、様々な手続きや届出を決められた期限内に行う必要があります。
その中で一番初めに届け出なければならない手続きが「死亡届」です。
この記事では「死亡届はどこでもらえるのか?」「いつまでに、どこに、誰が届け出る必要があるのか?」などについてご説明します。
また、銀行口座の凍結や死亡後に必要となる他の手続きについてもご説明しています。もしもの時に備えてあらかじめ知識をもっておきましょう。
死亡届とは?戸籍を抹消する手続きの内容と流れを解説
死亡届とは、正式には「死亡届書」と呼ばれるもので、ご家族や同居人の方が亡くなった際に、死亡したことを証明する書類です。死亡届によって亡くなった方の戸籍を抹消することになります。
また、死亡届を受理してもらわなければ、埋火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬を行うことができませんので重要な手続きとなります。
死亡届は市区町村の役所で手に入れることができますが、医師が死亡確認をする必要があるため、多くの場合は病院が用意をしてくれます。
なお様式はA3横書きで左半分が死亡届、右半分が死亡診断書です。
死後7日以内に提出すしましょう。ただし、国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内となります。提出しなければ葬儀、火葬ができませんので、すみやかに届出ることが必要ですが、多くの場合、葬儀社が届け出てくれます。
死亡届の届出人とは?なれる人は限られている
死亡届の届出人は誰がなるものなのでしょうか?ここで指す「届出人」とは役所に死亡届を提出する人のことではなく、死亡届が真実であることを証明するために署名、押印を行う人のことを指します。
届出人は次のいずれかの人である必要があります。
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 同居の親族以外の親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
死亡届を提出する前に!印鑑の用意とコピーの準備を
死亡届を役所に提出する前に、死亡届が提出できる段階かチェックしておきましょう。
- 死亡届の必要事項を届け人が記入・押印済み
- 死亡診断書または死体検案書に医師の記名・押印または署名がある
また後見人、保佐人、補助人および任意後見人が届出をされる場合はその資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本が必要となります。
死亡診断書とは、患者の死亡を確認して医師が作成する書類です。死亡診断書は、人の死亡を医学的かつ法律的に証明した書類ですので、死亡診断書がなければ、法的には死亡していることにはならないため、重要な書類となります。
なお、死亡事由によっては、死亡診断書ではなく死体検案書となりますが、診療継続中の患者以外の方が亡くなった場合や診療継続中の傷病以外の原因により亡くなった場合、例えば事故死などの場合は、死体検案書が交付されることになります。
死亡届を提出すると、役所で行われる手続き
死亡届を役所に提出すると、次のような手続きが行われます。
- 戸籍に死亡の記載がなされ、住民票が抹消される
- 葬儀、火葬、納骨の際に必要な埋火葬許可証が発行される
- 相続税法に基づいて翌月末日までに税務署に通知される
税務署への通知に基づいて死亡した人の遺産を推定し、納税義務があると認められる場合は、相続人に相続税の申告について通知がなされます。
つまり、銀行は死亡したことを知ったときに口座を凍結させることになります。
死亡届提出後に必要な9つの手続き
ここでは死亡届を提出した後に必要となる他の手続きについてみてみましょう。主な手続きとしては、次のものがあげられます。
- 世帯主変更届の提出
- 健康保険証または国民健康保険証の返却
- 後期高齢者医療保険者証の返却
- 介護保険被保険者証の返却
- 年金受給停止の手続き
- 生命保険金の請求
- 不動産の名義変更
- 公共料金の名義変更
- 自動車所有権の移転登録手続きる
1.世帯主変更届の提出
亡くなられた方が世帯主だった場合、市区町村は住民票の世帯主を別の人に変更します。多くは基本の優先順位付けの元、亡くなった世帯主の配偶者や世帯の年長者がなります。新しい世帯主に異存があるときのみ、遺族は帯主変更届の提出しましょう。
2.健康保険証または国民健康保険証の返却
亡くなられた方が協会けんぽや健康保険組合の健康保険に加入されていた場合は、保険証を会社に返却して喪失手続きをしてもらうことが必要です。
また、国民健康保険に加入されていた場合は、国民健康保険資格喪失届を14日以内に役所に提出して保険証を返却することが必要です。
3.後期高齢者医療保険者証の返却
亡くなれた方が75歳以上の後期高齢者である場合は死亡日から14日以内に役所に後期高齢者医療保険者証を返却してください。
4.介護保険被保険者証の返却
亡くなられた方が65歳以上または40歳以上65歳未満である場合は死亡日から14日以内に
役所に介護保険資格喪失届を提出して介護保険被保険者証を返却しなければなりません。
5.年金受給停止の手続き
年金を受けている方が亡くなられた場合、年金受給権者死亡届に死亡診断書(写)などを添付して死亡日からすみやかに日本年金事務所または役所に提出することが必要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として年金受給権者死亡届を省略することができます。
6.生命保険金の請求
生命保険に加入していた方が亡くなられた場合、加入先の生命保険会社に請求することによって死亡保険金が支払われます。必要な書類については生命保険会社に問い合わせてください。
7.不動産の名義変更
土地や建物などの不動産を所有していた方が亡くなり、不動産を相続する場合は、相続確定後に地方法務局にて登記簿の名義変更が必要となります。
8.公共料金の名義変更
亡くなられた方が世帯主の場合、電気、ガス、水道、NHKなどの公共料金の名義変更が必要です。口座振替で支払を行っていた場合、故人の銀行口座が凍結されていなければ、故人の口座から引き落しされることになりますし、凍結されていない場合は振替未納の連絡が届くことになります。
インターネットでも名義変更を行えるものもありますので、速やかに手続きを行うことが必要です。
9.自動車所有権の移転登録手続き
自動車の所有者が死亡した場合、自動車は相続財産となりますので、遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定次第、自動車所有権の移転登録手続きが必要です。
相続から15日以内に運輸支局または自動車検査登録事務所へ移転登録の申請を行いましょう。
もしもの時に備えて死亡届の知識をもっておきましょう
死亡届の提出と同時に銀行口座が凍結されることはありませんが、凍結される前に必要な現金は引き出しておくことが必要です。
また、郵便物については送付元にご家族が亡くなった旨を伝えておけば故人宛に送付されることはありません。
慌てずにお別れができるよう、亡くなったあとに必要な手続きも知っておきたいという方は「【死亡後の手続き一覧】家族や身内の葬儀後にやることチェックリスト」の記事も参考にしてみてください。



