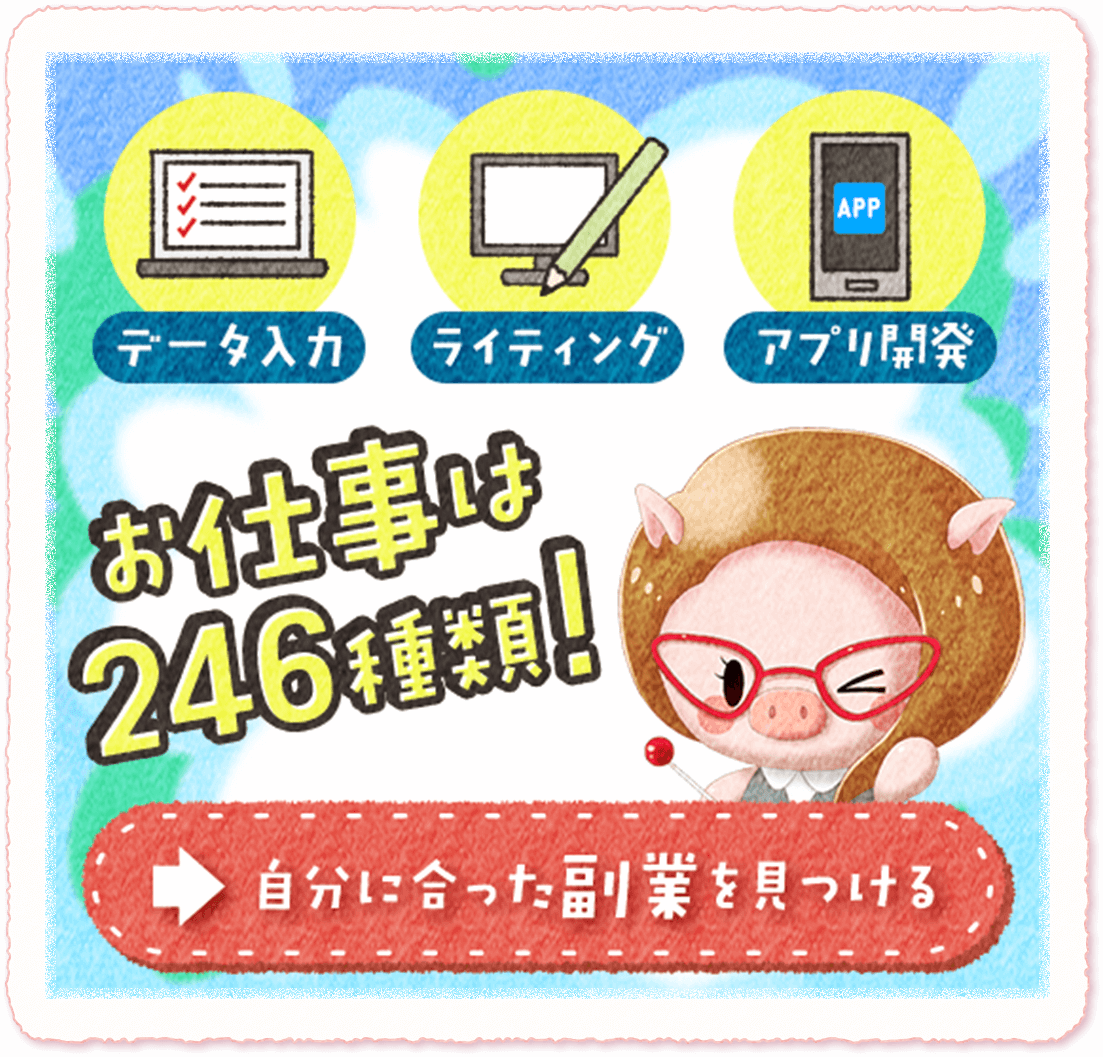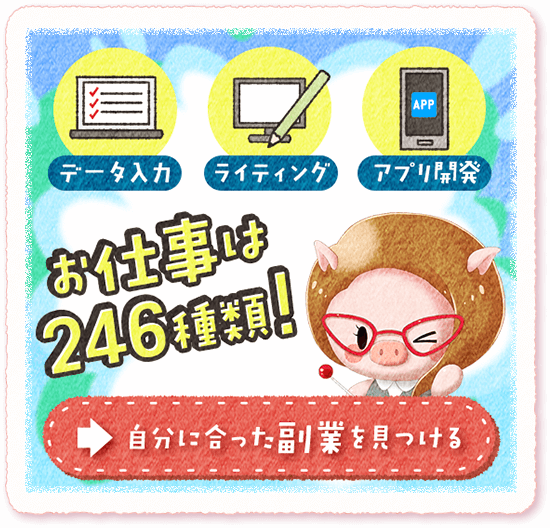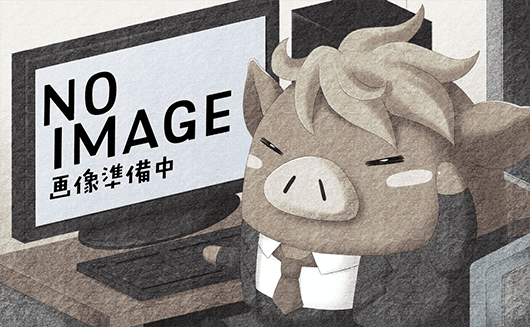
サラリーマンが個人事業主になるメリット・デメリット!開業方法も
会社員をしながら、副業をして稼ぎたいとお考えの方も多いのではないでしょうか?そこで気になるのが「個人事業主」として開業することです。
副業による収入が多ければ、個人事業主として開業するメリットを得られるケースがあります。
今回は、サラリーマンが個人事業主として開業する方法と、そのメリット・デメリットについて詳しく解説します。これから副業を始めたい方、副業をして収入が増えてきた方は、ぜひチェックしてくださいね。
サラリーマンをしながら開業するってどうゆうこと?個人事業主とは
個人事業主の定義
個人事業主とは、会社を設立せず個人で事業をおこなう人をいいます。
この「事業」とは、継続的に反復しておこなう仕事のことです。単発や一回のみの仕事は事業に該当しません。個人事業主として反復・継続的な仕事をし、得られた収入は「事業所得」に位置付けられます。単発の継続性がない収入の場合は、「一時所得」や「雑所得」に該当します。
事業所得であれば、確定申告で「青色申告」を選ぶことができ、節税効果が見込めます。
一時所得や雑所得には、赤字を繰り越すなどの制度がなく、税制のメリットは事業所得に比べて少なくなります。副業による収入が「事業所得」にあたるか、「一時所得・雑所得」にあたるか判断ができない場合は、管轄の税務署で相談するようにしましょう。
個人事業主と法人の違い
個人で事業をおこなう人を個人事業主といいますが、法人の場合は株主や出資者により設立した事業体のことをいいます。法人を設立するには、登記や定款を作成する必要があり、設立には数十万円の初期費用がかかります。
また、同じ事業をおこなう主体であっても、個人事業主と法人ではかかる税制も異なります。法人には法人の、個人事業主には個人事業主の、それぞれのルールのもと税金が課税されます。
サラリーマンが個人事業主になる方法!意外にカンタンな開業手続き
所轄の税務署に「開業届」を出すだけ
個人事業主として登録をするには、税務署へ「開業届」を提出する必要があります。まずはご自身のエリアを管轄する税務署を調べましょう。
管轄の税務署に、開業するために必要な資料「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。この書類は国税庁HPからダウンロードすることができるので、事前に記入をして税務署窓口に持っていくとスムーズです。
特に面倒な証明手続きや、費用は発生しません。
紙を提出するだけでその場ですぐ完結するので、だれにでも簡単に開業することが可能です。また、同じタイミングで「所得税の青色申告承認申請書」を提出することができます。この青色申告申請書の提出は任意ですが、提出することで節税効果がありますので、忘れず提出をするようにしましょう。
会社のルールを確認してから手続きしよう
税務署に届出書を提出するだけで開業できる個人事業主ですが、副業をするのであれば勤め先企業のルールをしっかりと確認してからにしましょう。
開業届を出すだけであれば、副業が会社にバレることはありません。
しかし、副業が禁止されている企業において、必要な手続きをとらずに開業し、副業による収入がバレてしまうと、勤め先で罰則を受ける可能性があります。会社によっては、降格や減給なども避けられません。必ず、社内の就業規則で副業に関するルールを事前に確認してくださいね。
サラリーマンで個人事業主になるとなにが変わる?税金と保険料
会社員をしながら個人事業主になり、副業で収入を得ると、収入によっては「確定申告」が必要になります。
基本的に、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
しかし、もし副業によろう所得が少なかったり、赤字が出てしまったりしても、給与所得と損益通算することが可能です。赤字が多ければ、会社で払いすぎた税金が返ってくることもありますので、副業による所得が少なくても確定申告をする人はいます。
サラリーマンしながら個人事業主になるメリットは「税金」
サラリーマンをしながら副業をし、ある程度の収入を得られるようになったら、個人事業主として所得を申告することで、節税することができます。
特に大きな節税効果が期待できるのは「青色申告」です。
青色申告とは、納付する税額を確定する「確定申告」の手続きでおこなう申告方法のひとつです。もうひとつの申告方法として「白色申告」があります。青色申告と白色申告の違いは以下の通りです。
- 青色申告特別控除がある(最高65万円)
- 帳簿付けが難しい
- 事前申請が必要
- 特別控除がない
- 帳簿付けが簡単
- 事前申請が不要
簡単にいうと、青色申告の方が税制メリットが大きい分、複雑な帳簿付けをする必要があります。節税効果を期待するなら、多少の手間や時間を考慮しても最大65万円の控除を受けられる青色申告がおすすめです。
事業にかかる費用を経費にすることができる
サラリーマンをしながら、個人事業主として事業をおこなうのであれば、副業にかかるさまざまな費用を「経費」として計上することができます。
経費としてみとめられる項目に、以下のような例があります。
- 事業にしようした携帯電話やパソコンの通信費
- 自宅を仕事場にした場合の家賃や水道光熱費
- 会食やカフェ利用などの飲食費
事業に関連する費用は、文房具や消耗品、家賃や水道光熱費まで「事業をおこなうために発生したもの」であれば経費にすることができます。
プライベートと仕事で兼用しているものの場合は「家事按分」として、事業に使った割合だけを経費として換算することができます。適切なルールのもと経費を計上することで、税金を払いすぎることなく上手に節税することができますよ。
家族に対する給与を「青色事業専従者給与」で経費にできる
個人事業主として開業し、青色申告をする場合は、家族への給与を経費にできるというルールがあります。通常であれば家族であっても、専従者への給与を経費にすることができません。
しかし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すると、生計を一にする15歳以上の親族への給与を経費として認めることができます。
もし、副業の事業内容によって人手が必要な場合、近しい家族であれば経費にできるというメリットを活かすとよいでしょう。
社会保険料の節約効果
サラリーマンをしていると、「第2被保険者」として社会保険に加入することになります。この社会保険料は、勤務先の4〜6月の給与をもとに支払額が算出されます。給与所得以外の副業による収入は、この社会保険料の計算対象にはなりません。
つまり、副業により収入が増えても、社会保険料が増えることはないため、賢く社会保険料を節約することにつながります。
サラリーマンしながら個人事業主になるデメリットは手間とリスク
毎年必ず確定申告をする必要がある
サラリーマンであれば、毎年会社が「年末調整」としておこなう納税額の確定手続きですが、個人事業主になると「確定申告」として自ら手続きしなければなりません。
毎年2月〜3月の一定期間の間に、1年間の収支を記入した書類を作成し、税務署へ提出をする必要があります。会社勤めをしている人には慣れない手続きですが、個人事業主として副業をするのであれば、欠かせないものとなるでしょう。
帳簿付けや決算書類作成の手間がかかる
自身で確定申告をし、青色申告で節税効果を目指すなら、面倒な帳簿付けを日々おこなう必要があります。近年では、会計ソフトやクラウドサービスが普及し、初心者でも取り組みやすい環境が整ってきていますが、それでも本業と並行しておこなうには手間と労力がかかります。
副業による仕事以外の、事務作業によって負担がかかり、本業へ支障が出ないようバランスをとることが大切です。
失業保険の受給資格を失う
サラリーマンであっても、個人事業主として開業した場合は失業保険を受けることができません。
失業保険とは、雇用保険のなかで失業中も生活を心配せずに仕事さがしができるよう、国から給付金が支払われる制度のことです。雇用保険に加入している人であれば会社を辞めた際に失業給付を受けることができますが、サラリーマンをしながら個人事業主になると、この失業保険の受給資格を失ってしまいます。
いざ仕事がなくなってしまったときに、国から受け取れる給付金がなくなるというデメリットはよく理解しておきましょう。
なお、個人事業主の廃業届を出すことで、事業開始前の雇用保険において有していた受給資格により、失業手当をもらえるケースもあります。詳しくは、管轄のハローワークへ問い合わせるようにしてくださいね。
ルール範囲ならOK!サラリーマン個人事業主なら節税も可能
サラリーマンであっても、個人事業主になることは簡単です。個人事業主になれば、経費をうまく利用して節税をしたり、青色申告による特別控除の恩恵を受けたりすることができます。
しかし、その一方で本業をしながらの時間調整や、手続きにかかる手間や労力をしっかり把握しておかなければなりません。
会社員でありながら開業することによるメリット・デメリットをまずは一度考えてみてくださいね。