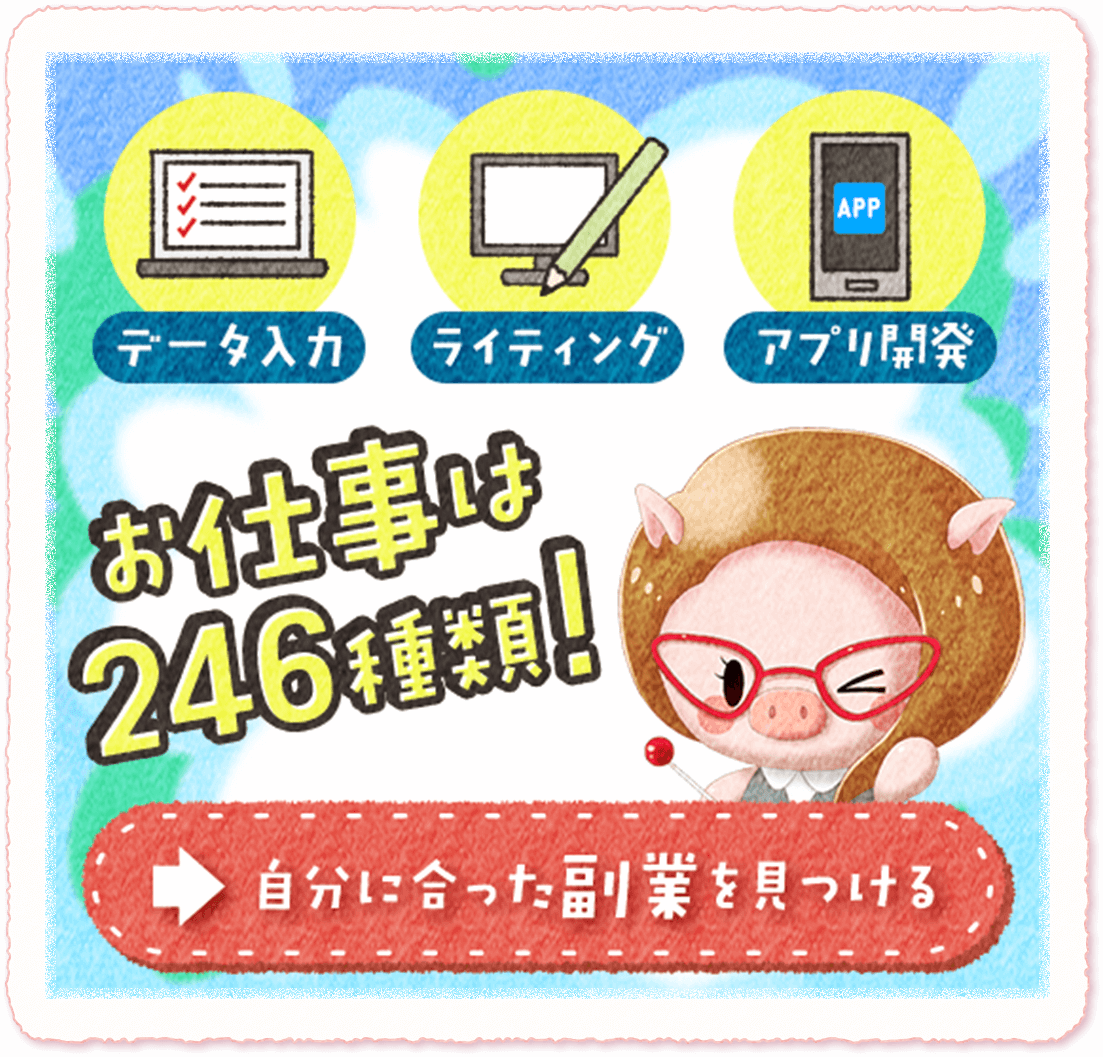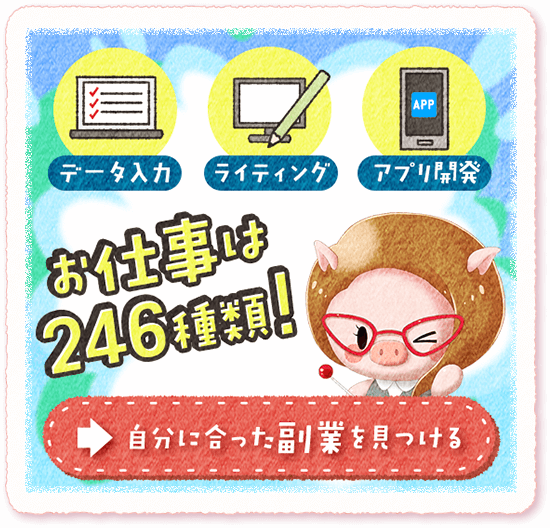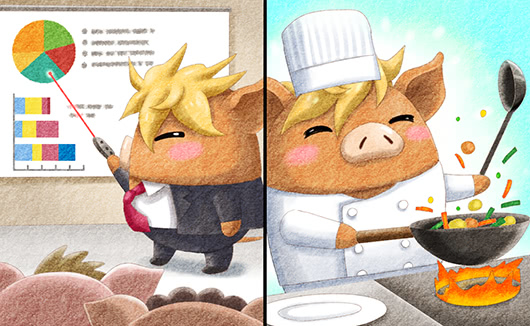
副業したら社会保険はどうなる?副業先から給与をもらうときの注意点
昨今、国は働き方改革の一環として副業や兼業の普及促進を図っており、副業を認める会社も多くなりつつあります。
そこで気になるのが「副業した場合、副業先でも社会保険に加入する必要があるのか」ということ。
実は副業先の会社や労働時間など、一定の条件によって社会保険に加入しなければならないケースがあるんです。
この記事では社会保険の加入条件や社会保険料について基本的な知識や、副業を始めるにあたってよくある疑問などについてしっかり解説していきます。
どのような働き方であれば社会保険に加入しなければならないのか、副業先を決める前に知っておくと安心ですよ。
社会保険の適用事業所とは?社会保険の加入条件をチェック
それでは社会保険の加入条件などの基準について確認してみましょう。
社会保険の加入は労働時間および労働日数と収入で決まる!
副業先の会社で常用的に使用されていて、次の条件に当てはまる場合は、副業先の会社でも社会保険に加入しなければなりません。
- 副業先の会社が社会保険の適用事業所であること
- 副業先の会社での雇用形態がパートやアルバイトなどの場合、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が副業先の会社で同様の業務に従事している一般従業員の4分の3以上であること
国籍や性別、年金の受給の有無は関係ありませんが、健康保険は75歳未満、厚生年金は70歳未満であることが条件です。
1週間の勤務時間が30時間以上かつ、1ヶ月の勤務日数が15日以上であれば社会保険に加入する義務が生じることになります。
ただし次の5つの条件をすべて満たす場合は、所定労働時間および所定労働日数が一般従業員の4分の3未満であっても社会保険に加入する義務が生じます。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金月額が88,000円以上であること(賞与、残業代、 通勤手当等は含まない)
- 学生(夜間、通信、定時制の方は除く)でないこと
- 常時501人以上の会社(特定適用事業所)に勤めていること
社会保険の加入は本人の意思に関わらず、上記の条件に当てはまるか否かで判断されます。
中には条件に該当しているにも、関わらず加入していないケースも。しかしこの場合は違法となり、年金事務所の調査などで発覚した場合は最大2年間遡って社会保険料の納付を求められる可能性があります。会社任せにせずに自ら確認しておくことが大切ですよ。
強制適用事業所・任意適用事業所の違い
副業先で社会保険に加入しなければならない前提条件は、副業先の会社が社会保険の適用事業所であることです。社会保険の適用事業所には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
(1)強制適用事業所
- 株式会社などの法人の事業所
- 従業員を常時5人以上雇用する個人の事業所(ただし、農林水産業、飲食店、接客業、理・美容業、旅館業、サービス業、法律・会計事務所などは適用対象外)
(2)任意適用事業所
上記(1)の強制適用事業所以外の事業所で、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所となることに同意し、会社が申請して厚生労働大臣の認可を受けた事業所
つまり、副業先の会社が上記のいずれかの適用事業所でない場合は、働き方に関わらず社会保険に加入することはできないことになります。
特定適用事業所(従業員数501人以上)の場合、社会保険の加入条件は異なる
特定適用事業所とは従業員数(社会保険被保険者数)の合計が1年で6ヶ月以上500人を超えることが見込まれる事業所をさします。
副業先の会社がこの特定適用事業所である場合は、労働時間および労働日数が一般従業員の4分の3未満であっても、一定の条件に該当すれば社会保険に加入する義務が生じます。
2016年10月より変わった社会保険の適用拡大
2016年10月より、パートやアルバイトなど(短時間労働者)の方に対して年金などの保障を手厚くする観点から社会保険の適用が拡大されています。
労働時間および労働日数が一般従業員の4分の3未満であっても、従業員数(社会保険被保険者数)が常時501人以上の会社(特定適用事業所)に勤めている場合、次のすべての条件に該当すると社会保険に加入する義務が生じることとなりました。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること(賞与、残業代、 通勤手当等は含まない)
- 学生(夜間、通信、定時制の方は除く)でないこと
副業先が特定適用事業所であるかどうかが、社会保険加入のポイントといえます。
従業員数500人以下の会社でも労使合意があれば特定適用事業所
副業先の会社が特定適用事業所であるかどうかの判断基準として、従業員数(社会保険被保険者数)が501人以上であるかどうかで判断することができます。
ただし従業員数が500人以下の会社であっても、労使合意によって労働時間および労働日数が一般従業員の4分の3未満のパートやアルバイトであっても社会保険に加入できる会社も存在します。
従業員(社会保険被保険者、短時間労働者4要件を満たす者)の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること。
会社は年金事務所などに労使合意のなされた同意書を添えて申出を行い、受理されればパートやアルバイトも社会保険に加入することができます。
社会保険の加入が必要になる副業、ならない副業
まずは会社の社会保険の被保険者数をチェックしましょう。
従業員数(社会保険被保険者数)が500人以下の会社
副業先の会社で、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が副業先の会社で同様の業務に従事している一般従業員の4分の3以上であること。
従業員数(社会保険被保険者数)が501人以上の会社または労使合意のある会社
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること(賞与、残業代、 通勤手当等は含まない)
- 学生(夜間、通信、定時制の方は除く)でないこと
一方、社会保険の加入が必要とならないケースは、上記の条件に当てはまらない働き方(労働時間や収入の基準以内で働くこと)に加えて次のような働き方があります。
(2)2ヶ月以内の短期で働く場合
(3)4ヶ月以内の季節的業務で働く場合(除雪作業など特定の季節のみに必要となる事業)
(4)6ヶ月以内の臨時的事業所で働く場合(博覧会など一定期間の事業)
(5)個人事業所で働く場合(ただし任意適用事業所である場合を除く)
(6)自営業(ただし、法人の場合は代表者であっても社会保険に加入する義務があります)
社会保険の扶養者になる場合は年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)などの要件がありますし、健康保険組合によって基準が異なる場合がありますので、要件をよく確認しておきましょう。
本業と副業、両方とも社会保険に加入しなければならなくなったときの手続き
ここでは本業でも副業でも社会保険の加入が必要となった場合、社会保険料額や支払い方法、手続き方法などについてご説明します。
月30万円の厚生年金保険料(本人負担分)は27,450円となりますので、次のように計算してそれぞれの給与より天引きされます。なお、健康保険料についても同様に計算されます。
(副業)27,450円×(10万円÷30万円)=9,150円
本業と副業ともに社会保険に加入する場合、届け出が必要となる
副業先の会社が社会保険の加入手続きを行ったのかを確認した後、本業の会社へ「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出するか、または直接、本業の会社管轄の年金事務所へ提出してください。
副業と社会保険でよくある5つの疑問を解決!
(1)社会保険料が上がらないように、副業をはじめる方法
ほかにパートやアルバイトなどで給与収入を受け取る場合は、社会保険の適用がない個人の会社で働くと、労働時間や金額などを気にすることなく働いても社会保険料を気にする必要はありません。
そして社会保険の適用がある会社であっても従業員数(社会保険被保険者数)が500人以下の会社であれば、一般従業員の4分の3未満の労働時間および労働日数で働くことができれば社会保険料を気にする必要はありません。
ただし501人以上の会社で働く場合は、労働時間が1週20時間未満、給与が月88,000円未満であることなどの範囲内であれば社会保険料を気にする必要はありません。
しかしながら、どうしても副業先で労働時間などの基準を超えてしまう場合は、副業先を分散するなどして働く方法も考えられます。
(2)本業と副業の健康保険証が2枚になることはないのか?
「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」には本業の会社を選択事業所として、副業の会社を非選択事業所として記入することになっていますので、選択事業所として記載された会社で健康保険証が作成されることになります。
(3)副業先で社会保険に加入すると、本業の会社に副業がバレる可能性は?
本業の会社に迷惑になることも考えられますので、就業規則に則って副業のことは伝えておいた方がよいでしょう。
(4)本業の会社でだけ厚生年金保険に加入することはできるのか?
雇用保険は本業と副業の両方とも加入する必要があるのか?
副業を始める前に社会保険について理解しよう!
そのため社会保険料は副業先の収入分、増大することになります。
副業を始めるなら社会保険がどうなるのか把握しておくことはとても重要です。会社まかせにしないで、あなたに最適な副業や働き方を検討してみてくださいね。